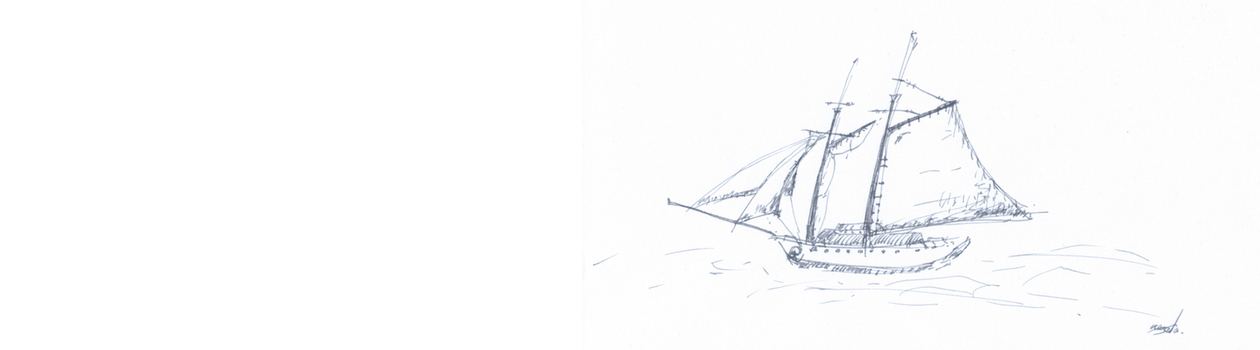ラムネを飲んでいた。微炭酸の甘い液体はほどよい刺激を残して喉に消えていった。
瓶の中には透明なガラス球がありなんとも涼しげに輝いている。ビー玉、”B級玉”はA級になれずにこんなところでひとりぼっちらしい。かわいそうに。でもそれも良いかもしれない。B級のほうが親しみやすい。みんなにかわいがられて、案外こいつは嬉しいのかもしれない。
夏は暑い。クーラーなしにはやっていけない。今年は特に暑いらしく、ニュースのキャスターは必死に熱中症予防を訴えている。死は身近にあるという。試しにクーラーを切ってみる。扇風機が首を振っている。
外で男の子が泣いている。理由はわからない。ただ泣きたいのか、なにかを取り上げられたのか。そういえば昔は簡単なことで泣いてしまった。夏休み、友達の家に泊まる約束、友達の家の環境が悪くなってしまい中止になった。何も友達が悪いわけではない。友達と自分は巻き込まれてしまった。理不尽と現実的な事実の間で、何時間も泣いてしまった。
当時、赤い繭という小説を読んだ。自分が家々を歩き回るうちに足から赤い繭になってしまうという物語だった。何を意味しているのか小さい脳味噌にはわからなかった。
自分は風船になりたいと思った。風船を膨らませた。できの悪い風船は地面へと落ちていった。何度上へ放っても、数秒後には重力の言いなりであった。軽い風船になりたかった。デパートで見た空に消えていく風船と、目の前の地面に落ちていった風船を比べてしまった。
また、理不尽に泣いてしまった。