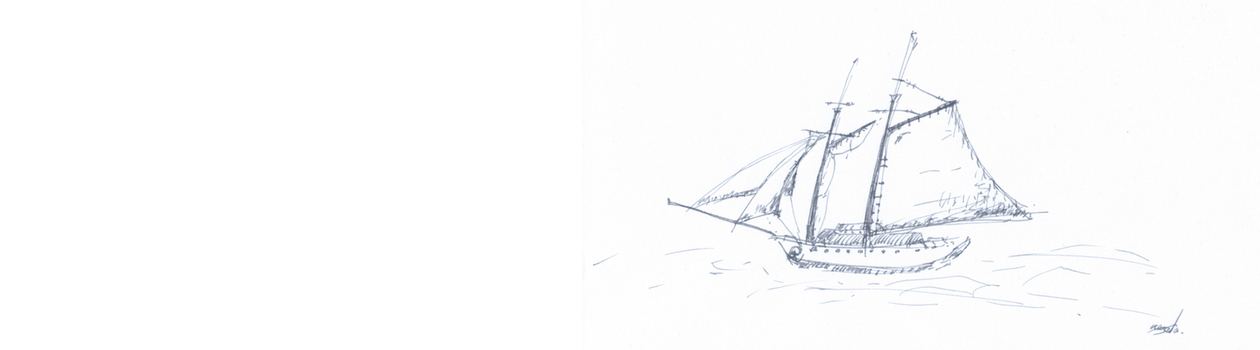「わたしは違います。函館は東京みたいに春一番が吹くわけでもないし、三月に桃や桜が咲くわけでもありません。だから、力ずくでも冬を終わらせるんです。今日が最後の雪かもしれないと思ったら、一番お気に入りの靴を履いて泥だらけになってでも、冬の最後を見届けます。それで、純白の雪に隠れていた吸い殻やペットボトルや動物の糞なんかを見て、『なんだぁ、醜い気持ちは雪の下に隠していただけなんだ』って思いながら歩くんです。それで、ちゃんと『さよなら』を言えたら、泥だらけになった靴を捨てます」
十二月の辞書 / 早瀬耕
モノでも人でも、やっていることでも、終わりをはっきりさせられる人がいる。その強さは必要ないと判断したものを捨てる勇気であるし、正解のないデザインを着地させること、元恋人の連絡先を消すことかもしれない。あるいは自分の最期に延命治療を断ることも、その一部かもしれない。自分はこういった人を強い人だと思うし、尊敬の念を持って接している。
冒頭の小説の引用では、彼女が曖昧な終わりという事象を意識して終わらせる中に、あえて美しいものを汚して捨てる美学、決別を描いている。自分ではこのようにできない。冬と雪とを何かに言い換えてもいいかもしれない。自分も、例えば醜い気持ちを言葉の下に隠すことがある。
自分はあらゆる部分を曖昧にして生きてきた。思想、趣味、言葉遣い、意志決定、それが為す人間関係である。そしてそれが終わるであろうとき、可能性という言葉を免罪符に、もはや再び手に入れようのないものであっても、そのほんのひと部分を捨てることなく手元に持ち続ける。そうすることで完全に失うことのない、楽しみや苦しみの過去の一部を持つ安心感、またどれだけ望み薄であっても可能性だけはあるという希望を得ることができる。
自分が自分でいられるために他人に依存することは不安定のように見えるが、実は依存先が多くなれば心理的安全性が高くなる。これは奔放に生きるための知恵と言うこともできるが、特異な曖昧性は自分という輪郭をすっかり失わせる。そしてこのような考えは一定のコミュニティにおいて「女々しい」と批判される。
だが、自分はこのスタンスを愛している。
都会的で現代的な理想の個人主義は自他の境界線がくっきりとして、自らの定義によって自らを形づくっている。資本主義が形づくった消費の反動か、あるいは情報化社会が生み出した没個性化への反感か、今この瞬間においてはそんな個人主義など虚構に堕ちてしまっているが、やはり足掻かずにはいられないだろう。メジャーではない小さな芸術畑にいた自分でも、個を主張するためにどれだけ人が苦労しているか少しは手に取れた。際だった個人であるために、一度他人を介して自分の強みを主張する。そうした方法で主張する必要があるのは自分自身が本当の一流ではないからだと、心のどこかで認識している。一部の人々は誰と戦っているのかもわからない苦しみを環境のせいにする。
おそらく、一度自他の境界線を見た人間が理想の個人主義の虚像を追わずにいることは不可能に近い。もしそれが可能ならば、このブログに来た人々はこのような文章を読んでいないだろう。決定された環境を受け入れ、文句を言いながらも逸脱することなく「幸せ」に生きられる時代はもはや終わっている。
水のように流れていたい自分にとって、境界線というものはあまり意識をしたくない。だからこそ冒頭のような自分と考えを異にする(線を引いているわけではない)人々を自分のなり得ない領域に達している人々として見ている。世界が自分である自分にとって、個が自分であるその人々を強い人だと認識している。おそらく自分がその視座に立とうとしても三下な人間で終わるだろうことも想像できる。そして一つの傲慢な我が儘として、自分のような考えを持つ人間がいることを分かって欲しい気持ちもある。そうしてこのような文章を書き続けている。
これを読んでくれている人々は、どのような視座に立っているのだろうか。個を定義することの苦しみに違う視点がある気がしている。いつも通り、幅広い批評を待っている。