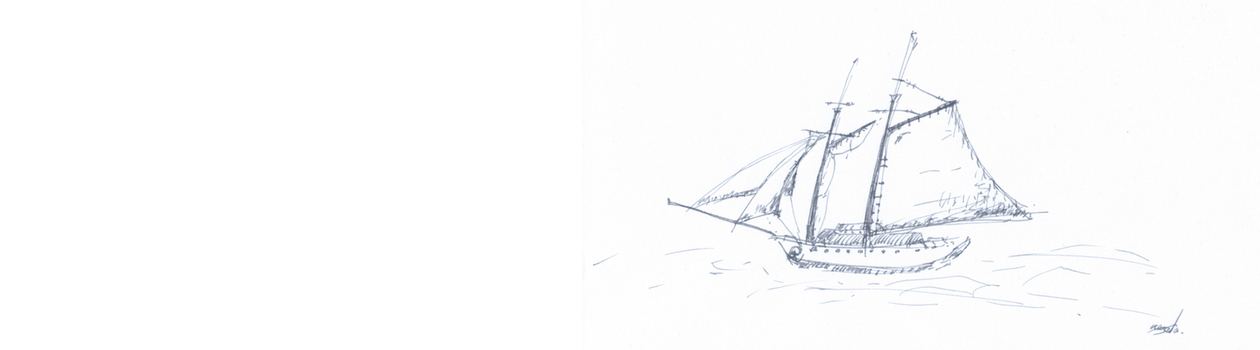その日は母親と些細な言い合いがあった日だった。年末の午後は2020年が最後の力を振り絞ったような寒波に見舞われ、車での帰省を諦めたほどであった。どうしても帰省せねばならない予定を抱えていた私は新幹線に飛び乗り博多を発ったものの、降雪と風の影響により列車は遅れに遅れ、ついには新岩国駅にておおよそ80分の停車を余儀なくされた。
これほどの寒波は珍しく、福岡だと数年にごとに同様のものがあるかという程度のものだ。3年前はちょうど大きな試験に向けて友人と勉学に励んでおり、その帰りは積もった雪道を原付とともに歩いた。先輩から譲ってもらったばかりの原付はキイキイと音を立てながら、ニュートラルのギアに重みを乗せてゆっくりと進む。家族向けのマンションが並ぶ深夜の住宅地で、まばらな街灯に照らされた雪が光を反射し妙に明るかったのを覚えている。あの時に一緒にいた友人は就職し会うことも無くなってしまったのだが、元気にしていそうだと言うことだけはSNSが教えてくれていた。
列車が動き出したときは既に夕方を回っており、そこで初めてその日何も食べていないことに気付いた。博多駅のコンビニエンスストアでサンドイッチを買うつもりだったのだが、すっかり忘れていた。そういえば先ほど列車販売が通ったと思い出し、パーサーが来るのを待って硬いアイスを買った。あまり意味の無い行動だと思うがお釣りはトレーで渡された。まあ、こういった小さいことが大切なのだろうか。普通のバニラ味ではなくせっかくなので限定の白バラコーヒー味にしたが、これがとても良く出来ており、チョコレートクッキーの層の下にコーヒー牛乳のような柔らかい味のアイス、ほろ苦いコーヒークリームが続く。新幹線の中ということもあり美味しい。しばらくして新大阪に着いた時には晩飯を考えてもいい時間であった。好物のカレーを食べて帰ろうかとも考えたが、別に母が用意をしてくれているらしく帰路を急いだ。
家に到着したとき、母は書斎にこもり仕事をしていた。来年度から随分と大きな仕事を任されるらしい。それに対しての準備を怠ることは許されなかった。次の〆切は年が明けた8日のため様々な文献を読みまとめている最中だという。もともと研究者であった母にとって仕事は活力の泉のようであり、本人も多くの仕事を抱えていることにある種の幸せを覚えているようであった。母は祖父を苦手に思っていた時期があったらしいが、この仕事気質に関してはまるで祖父と同様であり、その息吹は脈々と継がれていることを感じた。私は果たしてどうなのだろうか。
自分自身にも当てはまることだが、母は集中しているときに他人の話をあまり聞かない癖がある。今回も例に漏れず互いにあまりかみ合わない会話をしながら夜になった。年末であるので、テレビでは紅白歌合戦が流れていた。食事を終えて観ていると母はしきりにアーティストに関して聞いてくる。最初は丁寧にアーティストと曲を説明していたが、あまりに何も知らない母に全てを説明することに疲れ、適当にあしらうようになった。またかみ合わない会話を続けたが、ついには集中させてくれとしびれを切らし言い放ってしまった。母としては息子と話す数少ないチャンスを無碍にされたようなものだったろう、それはひどいんじゃないのと口論になった。私もやることの進捗があまり生まれておらず鬱憤が溜まっていたのだろう。たいしたことのない口論であるが、結果として、あまり良い年末ではなかった。
その晩、奇怪な夢を見た。
昼ではあるものの明かりの点いていない部屋を私は走っていた。何の目的があってか、ぐるぐると軽いランニング程度の速度で走り続けていた。誰もおらず何の音もない部屋で意味のない行動を続け、それに気付いたときには立ち止まり、またしばらくすると走った。全く夢らしい夢であるが、自身のその行動には何の疑問も抱かなかった。実際の私の部屋より二回りほど大きい部屋には私の部屋と同じベッドが置いてあった。あるとき私はそのベッドに寝転がった。突如、そこは夜になった。
明かりがないため部屋は暗く、何も見えないはずだった。しかしながらほのかな光が存在しているのか、枕と布団が存在しているのがわかる。ただ、自分がどこにいるのかはわからなかった。まぶたの裏に寝具が存在している、そのような感覚だ。そうしているうちによりはっきりと枕と布団を視認出来るようになった。近づくことが出来ないもののよく目をこらしてみると、そこには数十匹の黒い虫が静かに並んでいた。奇妙なことに人の影の形をかたどって整然と頭を揃えている。嫌悪感がわいた。何だこれは、一体これはどんな状況なんだ。すぐさま逃げたくなった。しかし逃げられなかった。より正確に言うと、逃げるような身体を認識していなかった。私はどうすることもできないまま虫たちを見つめた。どれくらいの時間が経っただろうか、襲ってくる訳でも動くわけでもない虫への嫌悪感はいつしか慣れへと変わっていった。そのとき自身の中に一つの考えが生まれた。ああ、この虫たちはベッドに横になっている自分自身なんだ。自分の姿を自分が見つめているだけなのだと。ではどうして俺はこんな姿になってしまったんだ、なぜこの姿を見せられているんだ。考えは尽きなかった。しばらく脳に汗を垂らして考えた。何も浮かばなかった。ついに考えることを放棄してしまった。ここに心の空隙が生まれた。その時だった。虫がゆっくりと後ろ肢を挙げ、逆立ちをし始めた。
朝になっていた。いつもより早い時間だった。
母の機嫌は直っていた。あるいはそう努めていた。私は寝ると感情がリセットされるタイプであるので、特に違和感や不和を感じることもなかった。しかし自身の夢に何か釈然としないままシャワーを浴び、洗濯を回し、朝飯にありついた。いつも通りの元旦であった。祖母を呼びおせちや雑煮、三宝を食べた。今年の正月料理は石川の郷土料理が入っていた。糀のついたカブの漬物にブリの身が挟んである。さっぱりとした漬物の味に滋味に富んだ魚肉が合う。朝から酒が進む。正月らしく屠蘇を飲み今年の多祥を祈った。料理を一通り平らげた後洗い物を済ませ、墓参りの準備に部屋に戻った。
着替えを済ませた後、私は床に何か落ちているのを認めた。全身に鳥肌が立った。
それは小さな黒い虫の死骸であった。