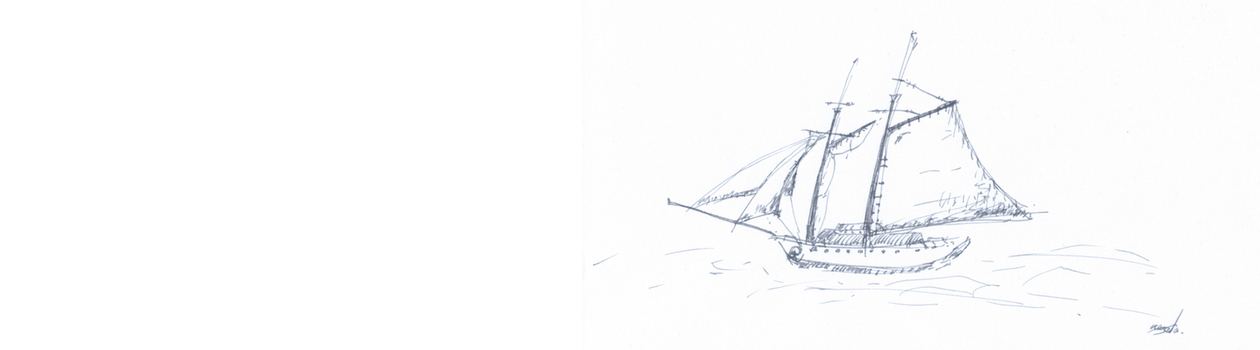過去のインターネットの夢と現状を隔てるものは多くあるが、最も過去のインターネットがそれを夢のようにたらしめているのは「インターネットは誰のものでもない」像を抱いていたことでないだろうか。誰かから情報を与えられるわけでもなく、⾃分から情報を仕⼊れにゆく⾏為、正解や規律は各⾃の裁量次第であること、どこか「森は誰のものでもない」に似ている。この意⾒と全く対極にある中国を考えてみると、インターネットをはじめメディアの情報は⾼度に統制され制限が加わっており、この状態はバーロウのいう独⽴と遠い位置にあることが⾒える。そのため確かに中国に⽐べると我々が普段触れるインターネットは独⽴で⾃由でなんとも素晴らしく思える。ただどうも単純な⾃由でないことは、⾁体がある現実と同じようである。
サイバースペースと表現したのはまだ黎明期にあるインターネットが現実空間に対して新たな⾃由の隙間が広⼤に広がる夢の空間だったからだろう。今となってはそのような夢の空間では無くなってしまったように思う(⼈間がそれを扱う限り、脳の限界をインターネットは超えられない)が、逆に⾔うと秩序づける存在があってこそ成り⽴つインターネットでもあるし、それが⽂明ないし⽂化を形作っているとも⾔える。⾃分はチキンなのでTor などを使うような深層ウエブに触れたことはなく想像の域を出ないが、果たして本当に⾃由なインターネット空間は⾃由と胸を張ることができるだろうか。⾃由は制限あってのものであるし、このような深層ウエブにおいては⾃らが規範を持って⾜を縛らねば、⼤きな怪我を招きかねない。管理者のいない深層では法もあったものでないし、それ故の⾃由も存在するだろうが、バーロウの述べる美しさとは違ったものと思われる。この⾃分の視点からすると、⾃分たちの世界のルールは⾃分たちで決めるという⽴派な独⽴宣⾔はこの20 年強で変わらざるを得なかったのだろうと考えられる。⾔い換えると我々は知らず知らずの内に誰かの作った仕組みに寄⽣し、⾁体と紐付ける情報をあえて対価として⽀払うことでインターネットで活動しているのだ。これは現実からの⼩さな独⽴なのかもしれないし、完全な独⽴とはほど遠い姿なのかもしれない。
数ヶ⽉前2 ちゃんねるの創設者ひろゆき氏が「やさしいSNS」の構想を述べ、たまたま参加する機会があったので輪に⼊れてもらった。そのSNS は⽉額料⾦を払ったものだけがコミュニティに参加出来る閉鎖型の「村」であり、⽉額料⾦の対価としてGoogleSuite に則ったサービスが提供される。⽴ち上げから2 ヶ⽉ほど在籍したが、⾯⽩いことが起きた。⾃由になんでも話そう、ルールは⼀つ「やさしくあれ」、という構想のうちに、統制の必要性が出てきたのだ。村には新規の参加者がどんどん集うが、村のコミュニティを維持し「やさしく」あるために古参の村⺠たちがルールを課していく。新規スレッドの制限、挨拶、「やさしく」ないものの排斥…完全な⾃由など、概念でしか存在し得ないものとなった。
ある⼈は全く空気が読めない⼈だった。この⼈は「建設的な意⾒」としてあらゆるものを柔らかく否定した。やさしく諭すつもりだったのだろうが、やさしい村⺠たちは次第に相⼿をしなくなっていった。それが村⺠たちのやさしさの結果であるにも関わらず、その⼈は逆説的にやさしさを享受できなくなり、いつの間にかいなくなってしまった。またある⼈はTwitter などの従来のSNS に視線を感じたらしく村に来たが、真に⾃由を感じることなくいなくなった。つまるところ管理者が「やさしさ」を課したあまりに全ての⼈が仮⾯をかぶることになってしまったのだ。この村も例に漏れず、相互監視になってしまったようであった。⼈間は完全に⾃由であることはできないのだろうと村は感じさせてくれた。この先、真に⾃由なサイバースペースが存在しうるのだろうか?