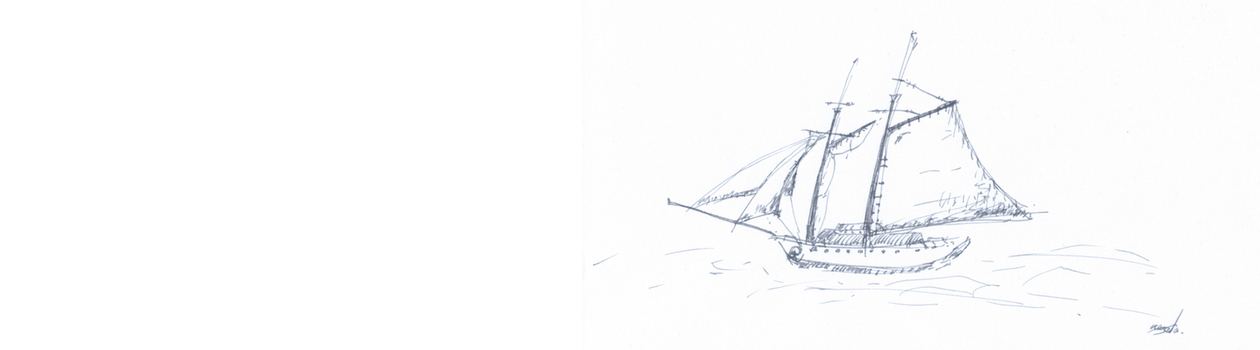今日は研究室にこもろうと思ったけども持ち前の怠惰を発揮し結局家で書類を見て終わった。かといって今この午前1時から研究室に行くわけにもいかず、かといって早起きのために寝るも寝付けず、こんな時は普段発さないようなことを発信する良い機会なのかもしれない。
人によってはかなり重い話に感じるかもしれないが、人間の致死率は100%、誰もが最後には死ぬわけでありいずれ避けては通れない話題ともあろうから書いておいて損はないはずである。
いきなりだが自分が3歳になるわずか前、父が夭逝した。父の働く大学の入学式のその日であった。特に大きな持病もなく、寝ている間の突然死だった。母の動揺はすさまじく、また教諭や教え子たちも状況を飲み込めないままただ時間だけが流れていたという。当時の学長が冗談だと思い家に駆けつけ、父が入学式で読むはずであった原稿を確認するも、やはり父はこの世にいないという現実を突きつけられるに終わった。自分はその時を覚えていない。ただ、菊の中に埋もれる父を見て「パパ」とだけしゃべりかけたという。幼すぎる自分には死がなんたるか全く理解できなかっただろう。
4歳になり、散骨に沖縄へと行った。旅行だと思っていたが、どうもそうではない。そう気付かせてくれたのは祖母のポーチから取り出された小さい紫色の巾着だった。どこだったか覚えは無いが、さびた桟橋から非常にきれいな珊瑚礁の海へと灰と骨を落としたことだけ覚えている。灰は風になってしまった。骨が沈んだかは覚えていない。「こんなに軽くなって」と伯父は泣いていた。伯父にとって手に付いた粉と生前の父は「違うもの」ではなかった。形は違えど同じ人であった。
それから何回か沖縄へ行った。毎回楽しい旅行だった。楽しかったのは自分だけだったかもしれない。料理の得意な祖母は卵を割るのに失敗したし、しっかり者の祖父はホテルのカードキーを無くした。
父のいない生活に周りが慣れてきたころ、曾祖母が亡くなった。大往生であった。大きな病気では無かったが寄る年波には勝てず、自宅で眠るように安らかに旅立ったという。明治生まれの曾祖母は厳しく、子供の自分は少し怖く思っていた。亡くなる1週間前、偶然にも祖父母と曾祖母を訪ねていた。この時珍しく別れ際に握手をしようと言われた。車の窓越しに握った手は冷たく、硬かった。葬式では納骨せず帰った。暴風雨の中運転した祖父は車の中で多くを話さなかった。「おばあちゃんはお迎えのこと、わかっとったんやろか」そんなことは知らない。でも、そんな気はした。
いつの間にか自分の中で死に対する考え方が出来ていた。人は簡単に死ぬし、突然死ぬ。でも死ぬことは身体が動かなくなるそれだけなのか、そうではない。死は日常にある。日常で死んだ人がいない生を実感して初めて死が成り立つ。逆に死が消えて無くなることならば、その人が記憶にある限りその人は生きている。死は生に内包されている。
中学の頃は父がまだ生きているとして話していた。あまり友人に気を遣わせたくなかった。だましたいわけではないけれども、未だに父が健在だと信じている友人がたくさんいる。申し訳ないと思う。中学生の時期に死生観なんて語るべきではないと思っていたし、一度ついた暗い嘘はもう挽回できない。死を明るい話題に変える話術なんて持っているはずもなかった。そう思っているのは自分よがりで、何よりも友人を深く信用出来ていなかった確固たる証拠なのだと後に気付いた。もう遅かった。
今度は伯母が亡くなった。自分が高校生の時だった。優しく、慈愛という言葉そのものの人であった。今度は病院で亡くなった。亡くなる1ヶ月ほど前だったか、一人で4時間ほどかけて見舞いに行った。旅行以外で新幹線に一人で乗るのはそれが初めてだった。体調を崩したという伯母を見舞うことも久しぶりに会える興奮とひとり旅の高揚感で少しわくわくしていた。病室で会った伯母は非常に元気だった。はつらつとしていてとても病人とは思えない具合だった。途端に自分は伯母の心配を忘れ、きっとすぐに全快するだろうと確信した。話をした。学校のことや当時付き合い始めたばかりの恋人のこと、勉強、将来の道、退院したときに行きたいところ。伯母は笑顔で聴いていた。貨物列車が遠くを通った。何両か数えた。ふと帰りの電車を思った。もとより日帰りのつもりだったし、次の日は恋人に会える。「じゃ、帰るわ!おばちゃん元気でよかった。明日予定あるから、この辺で失礼します。」伯母は少し寂しそうな顔をして「もう帰るん?会えて嬉しかった」と言ってくれた。最後になると分かってたら、そこで帰ってはいなかった。思えば、上体を起こしていた最初とは違い最後らへんは寝そべっていたし、検査入院というのは大学病院の個室に入っていた時点で嘘だし、窓際に飾っていた母からの贈り物はベッドから見て楽しむものだった。
母のショックは大きく、生活にハリが無くなった。支えられるのは自分だと思ったが、安易な言葉はかけなかった。かけられるものでもなかった。死は共感できないものだと感じてしまっていた。母がその時に共感を求めていたかはわからない。あまりわかりたいわけでもない。「忘れない限り生きているよ」とだけ言った。「忘れないよ」と返ってきた。
自分は時々、自分が持つ驚異的な運が父によってもたらされたものだと思うことがある。20年そこらしか生きていないが、不思議と重要な局面で運に助けられるのだ。何故かはわからない。実力が運に繋がっているだけかもしれないが、霊的なものをあまり信じない自分がこうも父に感謝している事実は自分でも特異なものであると認識している。
一昨年、祖父が亡くなった。病院だった。体調を崩す前は耳も良く足も丈夫で良く食べ常に知識を求め静かに笑っていた。病院では、違った。祖父は祖父のようではなかった。ほとんど寝ている中で、数分だけ起きた祖父と会話した。あまり会話にならなかった。今までよく見てきた祖父との違いに少し唖然としたが、どうしようもなかった。病院は人を病人たらしめると感じた。今度は少しだけ覚悟した。最後かもしれないと思った。最後になってしまった。火葬前しばらく棺に手をおいていた。祖父と作った竹とんぼを思った。小さな思い出だが他の何よりも形見たるものになった。自分は人に何を残せるのだろうと思った。人の中に自分が残したものが、肉体が無くなっても生き続けることがいかに素晴らしいことなのか見えた。自分は人に何を残せるのだろう。自分は人の中で生きることができるのだろうか。