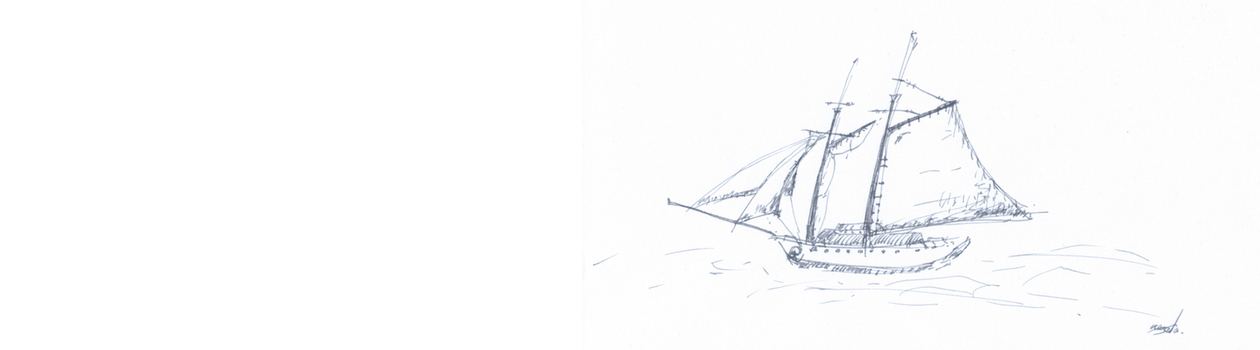家に帰ったとき、一通の無機質な封筒が届いていることに気付いた。父方の伯父からの手紙だった。伯父からの手紙はいつも簡潔で、筋道が立っている。薬学に傾倒しているだけある。けれども今度の手紙は少し毛色が違うように感じた。
墓のことであった。
祖父が高齢だったこともあり、父が亡くなってから長く伯父が当代を担ってきた。家に関わる決定はほとんど伯父の判断に委ねられた。寺、墓、慶弔事、土地、家屋、結縁離縁、さまざまなことは大勢の意見を参考にしつつ、最終的に伯父がこなしてきた。しかし伯父ももう軽快に動けるというわけでは無くなった。病気が身体を蝕み、思ったように行動できないという。数年前は後期高齢者の仲間入りだと笑っていたが、最近の伯父は自分の周りを整理することを意識し始めていた。
自分も最近ある程度覚悟していたが、そろそろ代替わりをしようとのことだった。当家はもう若い男性が自分しかいない。名を継ぐ、男である、ということは昨今時代遅れと捉えられがちだが、民法上仕方ない部分もある。若くてどこにでも動け、時代の潮流に乗ることができるのはもはや自分しかいない。古い考えと思われるかもしれないが、母は「別の家」であるため大きく出られない。次期当主はどうあっても自分なのだ。
分家として自分たちは生きているが、本家で数えれば25代が当代である。大きな家ではないのでもはや自分がどこに属しているかもはっきりしていないが、長くあることは確かだ。その26代となると、見えない重みが大きく大きくのしかかってくる。弱冠22歳には早すぎる、重い重い責務だ。誰かが死んだらその手続きは全て自分に任される。悲しんでいる余裕などないかもしれない。誰かが生まれたらすぐに会いに行く。遠い親戚が遠くなくなる。家を継がねばならない。家の記憶を絶やしてはいけない。
伯父は当家の墓ではなく、永代供養の合同墓に入りたいという。現在の墓の位置と伯父の居住地は離れているため、既に他の家に入った娘たちに墓を管理させるのは難しい。考え抜いた末の悲しい決定である。だが当代が自分となるとその決定を無視して当家の墓に入れることもできる。どちらにせよ最終判断は自分になる。財産関係を含め、様々なことの最悪の事態を想定しておかなければ危うい。
正直自分には何をどうすれば良いのかはわからない。家は大事だがどこかでそれが全てではないと思っている。甘いのかもしれない。それを知るのが刻一刻と近づいていることが怖い。だが、向き合わねばならない。